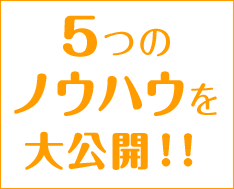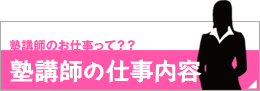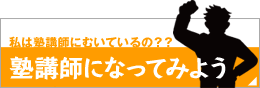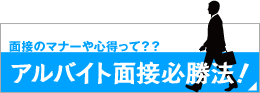一流講師の教え方
楽しい授業で生徒を引き付けるコツ

楽しい授業と言うと、おもしろい冗談を言って、腹を抱えて笑うような授業をしなければいけないと思っている塾講師の方も多いようです。
でも、それはごく一部の特殊な授業。
一般的には、生徒が日ごろ興味を持っていそうな話題について「雑談」レベルの話ができるだけで、ずいぶんと授業の楽しさが違ってきます。
部活の話、休日にどこかへ遊びに行った話、最近見たテレビの話。さすがにゲームの話題は教育を行う学習塾として不適切だと思いますが、漫画の話程度でしたらセーフかも知れません。ワンピースやドラゴンボールを読破している塾講師は、この点では強いかも知れませんね。
また、こういった話題以外にも、「話し方」に気をつけると楽しい授業になることが多いようです。怒った授業よりも笑顔の授業の方が好まれますし、生徒の目を見て話す方が塾講師の気持ちがよく伝わります。
生徒が話を聞いてくれない
生徒が騒がしくて聞いてくれないケースと、生徒がボーっとして聞いてくれないケースがあると思います。ここではその対処方法をお伝えします。

生徒が雑談したりして騒がしいケースには、絶対にきちんと「叱る」べきです。
一度叱ってもまだ繰り返す生徒については、正社員の方達と相談しましょう。ときには保護者を巻き込んだ対応になることも多いですし、あまりにひどい場合には、生徒に塾を辞めてもらうこともあります。
塾は何人もの生徒が集まる場所。しかもみんなお金を払って授業を受けています。他の生徒への悪影響も考えて、毅然とした態度を取りたいですね。

体調不良や、部活の疲労で生徒がウトウトしてしまうことはあります。体調不良や病気の場合は仕方がないので、家に帰すといいでしょう。
疲労によるウトウトは、やはりいったん注意しつつ、教室の換気をしたり、立ち上がらせて軽い体操をさせるといいでしょう。
生徒の成績を上げるには?
「生徒に対する情熱が一番!」と言いたいところですが、残念ながら情熱だけでは成績は上がりません。これはとても大切なことです。ここでは大きく2点をお伝えします。
生徒のレベルに合わせた授業を心がけましょう。
よくある間違ったケースは、生徒のレベルを無視した授業をしてしまうことです。
もともと成績のよい生徒に対しては、どれだけ詰め込んでも、どんな解説をしても、生徒の吸収力が高いので、比較的成果に繋がりやすいです。
しかし、成績があまりよくない生徒に対して、詰め込みや、レベルの高すぎる解説をすると、生徒は理解できません。こう言うと当たり前なことのようですが、生徒に情熱を注げば注ぐほど、こういった「教えすぎ」な問題が出てきてしまうのでやっかいです。
難しい問題や、いわゆる奇問については、臨機応変に割り切ってバッサリと切り捨てる勇気を持ちましょう。進度を意識した授業を心がけましょう。
例えば定期テスト対策。当然試験範囲が設定され、その範囲をまんべんなく指導することが、成績アップへの近道です。
しかし、生徒の理解度が低い場合、どうしても特定の単元に留まってしまい、なかなか先へ進めないことがあります。これは単純な問題のようで、よくある間違いパターンです。
全体のバランスを見渡して、進度を優先した授業を行うことを心がけましょう。どの教科が一番成績を上げやすい?
プロの塾講師としては、全ての教科の成績を上げなければなりません。
そのためには、各教科の「特徴」をよく理解する必要があります。この各教科の特徴を考える上で、大切な枠組みは、「積み上げ科目」か「暗記科目」かという点です。

「積み上げ科目」とは、英語や数学に代表されるように、学習した単元が、その次の単元の「土台」になっているような構造の科目です。例えば英語ですと、アルファベットの学習→単語の学習→一般動詞やbe動詞の学習→過去形や未来形の学習… といったように、ほぼすべての学習が繋がっています。
また、数学ですと、四則演算→分数や小数点の計算→多項式の計算→一次方程式→二次方程式→放物線のグラフ… などのイメージです。
科目別にその特徴と指導のポイントをまとめてみました。
| 科目 | 科目の特性 | 指導のポイント |
|---|---|---|
| 英語 | 積み上げ科目 | 単熟語の暗記は生徒に任せ、チェックは塾講師がするといいでしょう。それ以外の文法や長文の学習に近道はありませんので、日々の学習が不可欠です。 |
| 数学 | 完全な積み上げ科目 | 数学にも近道はありません。まずは昔に学習したはずの全ての単元の理解度をチェックして、忘れているところを必ず補習してから新しい授業をするようにしましょう。 |
| 理科 | ほぼ暗記科目 | 一部数学的な要素もありますが、暗記科目として割り切り、テスト前に集中して暗記する方が点数に結びつきやすいようです。 |
| 社会 | 暗記科目 | 歴史ではそのストーリーを語ったり、地理では地域毎のエピソードを伝えると面白い授業にはなりますが、成績に直結させるためには、単純に暗記を繰り返す方がよいようです。 |
| 国語 | 読解以外は暗記科目 | 読解力は一朝一夕には伸びません。漢字や文法事項などの暗記項目を確実に学習することが重要です。 |
塾講師のプロが伝授する秘術!
とても奥の深いプロの塾講師の秘術。ここでは、比較的簡単に真似のできる秘術を3つ紹介します。
黒板をたたいてみましょう!
生徒の集中力を高めるちょっとしたワザ。これぞ大切!といったところで、その大切な文字のあたりを「ドンドン」とゲンコツで叩きます。
イメージとしては、黒板をドンドン!→クルっと生徒側に振り返る→「これ大切ね!」という感じです。
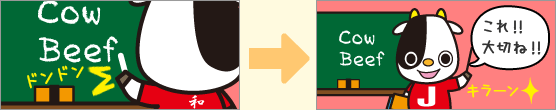
授業にメリハリが出て、生徒の記憶にも残りやすいやり方です。
個別指導の場合には、黒板をテキストやノートに置き換えて、ゲンコツを指に置き換えて、「トントン」と叩くといいでしょう。指でも結構な音が出ます。
ただ、使い過ぎと強く叩きすぎには注意です。
とことんほめてみましょう!

秘術というにはあまりにも定番なようですが、プロはとことんほめています。プロはほめる回数が多いのはもちろんですが、ほめ方が具体的であることが特徴です。
ほめる回数については、実際に自分の授業で何回ほめているか数えてみるといいでしょう。プロの塾講師の中には一回の授業で50回以上もほめていることがあります。
具体的なほめ方については、問題が解けたとき以外では、いったい何をほめていいのか分からないケースもあるようです。しかし、学習に関係のない事柄でも、生徒はほめられるとうれしいもの。たとえば、「今日のシャツかっこいいね!」「あいさつが元気でいいね!」「字がきれいでいいね!」など、生徒をよく観察すれば、いくらでもほめるところは見つかります。
教室を歩き回ってみましょう!

これは一斉指導において、生徒の集中力を高める秘術です。
塾講師の中には、ずっと黒板の前で授業をしている人もいますが、それでは単調になってしまいます。教室を歩き回ることを「机間巡視」という言葉があるように、教育者のノウハウとして重要なものです。
まずは、生徒の演習中に机間巡視をすることからはじめましょう。その次に、講義をしながら、つまり話しながら歩き回ってみましょう。
講師が近くに来ただけで刺激を受けて背筋が伸びる生徒もいますし、仮に講師が近くに来なくても、聞こえて来る声の方角が変わるだけで、脳を刺激します。